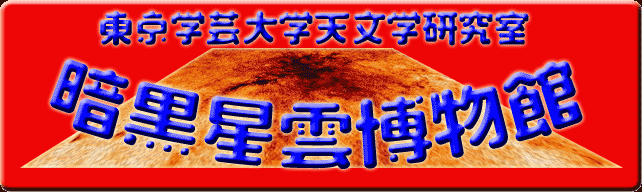 最初の画面にもどる
最初の画面にもどるCopyright(C) Tokyo Gakugei University Astro Laboratory, 2001. All rights reserved.
3. 暗黒星雲画像の作成
3.3 星数密度分布図
銀河座標に沿って2分角の格子(グリッド)を作り,各々の格子の中に含まれるある一定以下の等級(しきい値)をもつ星の数を計測することにより,DSSプレート毎に星数密度分布図を作成した.等級のしきい値は,北天のRバンドと南天のBjバンドのプレートでは19等,南天のVバンドのプレートでは16等とした.隣接するプレートの星数密度分布図をつなぎあわせ,3種類のバンド (R, Bj, V) 毎に一つながりの星数密度分布図を作成した.ここで得られた星数密度分布図は,バンド毎にカバーしている天空での領域が異なり,また,星数密度分布図を作成する際に用いた等級のしきい値も異なる.北天をカバーするRバンドの星数密度分布図と,銀河中心方向以外の南天をカバーするBjバンドの星数密度分布図は,天の赤道付近で約6°の幅のオーバーラップをもつ.また,銀河中心方向をカバーするVバンドの星数密度分布図は,Bjバンドでカバーされている領域にすっぽり囲まれており,その間には約2°のオーバーラップがある.天の川全体をカバーするひとつながりの星数密度分布図を作成するために,Bjバンドの星数密度を基準に,RおよびVバンドの星数密度を定数倍し,3種類の星数密度分布図をつなぎ合わせた.定数倍する際の係数はBjバンドとRバンド,および,BjバンドとVバンドの星数密度分布図がオーバーラップしている領域での(それぞれのバンドでの)星数密度の比を測定して求めた.以上の結果,銀経:0°〜360°,銀緯:−40°〜 +40°の広大な範囲をカバーする星数密度分布を描き出すことができた.
暗黒星雲は,星の数の少ない暗い部分として認識される.星数密度分布図は2分角という高い分解能で描かれている(フルスケールでの画素数は10,800×2,400ピクセル).この高い分解能を実現したため,天空に広がる暗黒星雲の分布を細部に至るまで描き出すことができた.
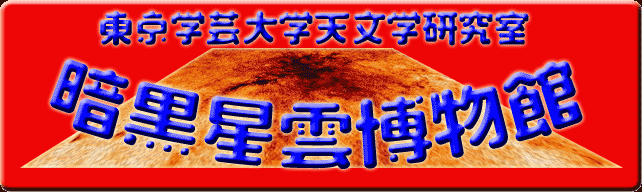 最初の画面にもどる
最初の画面にもどる
Copyright(C)
Tokyo Gakugei University Astro Laboratory, 2001. All rights reserved.